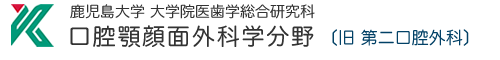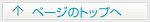学部教育
歯学部臨床系科目 口腔外科学(2) 講義シラバス
| 対象学年 | 後期、前期 学期 4年次、5年次 (平成 年入学者) 前期 学期 4年次(平成 年以降入学者) |
| 講義者 | 中村典史、野添悦郎、石畑清秀、石田喬之、岐部俊郎、鈴木甫 担当教員 |
| 授業概要 | 歯科医師として必要な口腔ならびに顎顔面外科学、および口腔外科手術のための全般的知識を教授する。 |
| 一般目標 | 1.口腔、顎、顔面ならびにその隣接組織に現れる先天的ならびに後天的疾患について、その原因、病理、症 候、診断、治療および予後について教授する。
2.各種疾患の診断と治療方針の決定に際し、全身症状を関連させて理解できる素養、およびこれらの疾患の予防に関する知識を身につけるよう教育する。 3.口腔および口腔に関連する器官に発生する先天的および後天的異常、外傷、炎症、口腔粘膜疾患、神経疾患などの各種疾患に関する総合的知識の取得と代表疾患の診断ならびに治療方針の策定などができることを目的とする。 4.抜歯術,インプラント,歯槽堤増堤などの口腔外科手術の基本的知識と手術手技について理解が得られるようにする。 |
| 到達目標 | 1. 口腔・頭蓋・顎顔面領域の発生を概説できる。
2. 口腔・頭蓋・顎顔面領域に症状をきたす主な先天異常を説明できる。 3. 口唇・口蓋裂の病態と治療方針を説明できる。 4. 口腔・頭蓋・顎顔面領域の成長・発育異常(不正咬合)を説明できる。 5. 一般的な骨折の種類と特徴および治癒過程を説明できる。 6. 歯の外傷と顎顔面骨折の原因と種類を列挙できる。 7. 歯の外傷の症状と検査法を列挙し、診断と治療法を説明できる。 8. 骨折の治療原則を説明できる。 9. 口腔粘膜疾患の種類と特徴を説明できる. 10. 歯性感染症の原因菌と感染経路を説明できる。 11. 主な炎症を概説できる。 12. 口腔・顎顔面領域に症状を現す感染症の種類とその症状を列挙できる。 13. 顎関節疾患の種類と特徴を説明できる。 14. 唾石症の特徴、症状および治療法を説明できる。 15. 三叉神経痛の特徴、症状および治療法を説明できる。 16. 顔面神経麻痺の特徴、症状および治療法を説明できる。 17. 抜歯の適応症と禁忌症を説明できる。 18. 抜歯に必要な器具の用法と基本手技を説明できる。 |
| 授業のレべルと履修要件 | 口腔外科学の講義内容を理解するためには、口腔解剖学・発生学・口腔組織学・口腔生理学・口腔病理学などの専門基礎科目の知識は不可欠である。また一般外科学・耳鼻咽喉科学などと関連する領域が多く、内科学的な知識も要求されるため、これらの医系関連臨床科目の知識も必要である。 |
| 判定方法 | 2/3以上出席した者に対し,半期毎の講義の最終回に筆記試験を行う。 評価は中間試験50点、期末試験50点とし、合計60点以上を合格とする。 |
| オフィースアワー | 毎週火曜 16:30~17:00 臨床研究棟4F 口腔顎顔面外科 第1研究室その他 |